9月 ×日(曇)
ようやく一息つきました。
今年の8月は忙しくて、HPを更新する時間がありませんでした。
(T_T)/~~~
今年は「節電の夏」だったせいか、別荘のみなさん、例年と比べわりと早い時期から軽井沢入りしていたみたい。
軽井沢も近年暑くなっているといわれるけど、それでも都内近郊と比べたら格段にしのぎやすいですからね。
7月 ×日(曇)
今日は5ヶ月齢のミニチュアピンシャーのさくらちゃん(♀、1kg)の手術日です。
おてんばさんのさくらちゃんは、玄関先のシューズ
クロークから飛び降りて左の前肢、トウ骨と尺骨を折ってしまいました。
さくらちゃんは小型犬の仔犬ですから、折れた骨の直径はわずかφ3mm程度しかありません。この手の非常に細い骨は単純な外部からのギブス固定だけでは絶対癒合しませんから、手術で骨折端同士をきっちり着ける必要があります。
というわけで、本日の手術では、おそらく臨床家が扱う整形外科機材のうち、最も小さなプレートとスクリューを用いることになりました(下の画像、ボールペンとの比較)。
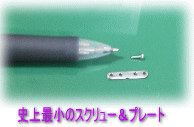
スクリューは直径φ1.5mm長さ6mm、一方プレートは幅4mm長さ19mm。
この手の手術は細かな作業が連くうえ、ドリルの場所ひとつ誤っただけで修正が利かず失敗ですから緊張の連続です。
- 正確に位置を決めるとφ1.1mmのドリルで下穴を開けて、さらにφ1.5mmでタップを切る、デプスゲージで深さを確認後適合するスクリューで固定していく -
こんなややこしい作業の繰り返しですが、人間の適応力とはふしぎですね、最初こそ小さすぎてやや戸惑うものの、毎度のことですが、のってくると小さいことなんか、全く苦にならなくなってしまいます。
極端な話、1.5mmの穴が3mmくらいの大きな穴に見えてくるから不思議です。
7月 ×日(曇)
たて続けにわんこの帝王切開を行いました。
昔から「犬の安産」というけれど、これも犬種によりきりで、少なくとも短頭種、例えばブルドックやボストンテリアは難産が当たり前。
というか、帝王切開以外では無理というのがこの世界の常識。
なぜ無理なのかは、以前NHKの「いのちドラマチック」で、分子生物学者の福岡伸一先生が力説していたので、一般の方でも知ってる人は知ってるみたい。
ちなみに今回の患者さんはボストンテリアとフレンチブルドック。もちろん典型的な短頭種。しかも、いずれも胎仔がひとつだけで、そろいもそろってハイリスク患者。
ワンコの場合、出産24時間前になると顕著に体温低下が認められるのですが、胎仔数が少ないケース(=1頭)では、基本的に胎盤から分泌される分娩を誘起するホルモンも少ないため、目安の体温低下が明確になりません。
というわけで、体温が当てにならない以上、エコー画像上の胎児の大きさと胎児の心拍数を基準に、もっとも母子ともにリスクの少ない時を見つけて手術に踏み切りますが、これが結構難しい。
もっとも、私はアマノジャクで難しければ難しいほど気合が入るタチなので、手術自体は嫌いじゃありません。今回も無事終えることが出来て本当によかったと思う。
「帝王切開はけっして珍しい手術ではありませんが、かといって他の外科手術と比べて数が多いものでもありません。それだけに、臨床家としての腕の良し悪しがはっきり見て取れると思う。」・・・・・ある有名な教授のコメントです。
7月 ×日(晴)
軽井沢とはいえ連日暑さが厳しいので、今日からスタッフ一同外科のスクラブスーツ着用で仕事をすることにしました。
当院流のクールビズです。
今月は異様に手術が多くみんな疲れ気味ですが、そんなときでも仕事が楽しく、かつはかどるようにと、女性スタッフは鮮やかな花柄のデザインを採用し、一方私といえば、思い切ってかわいい動物柄にしてみました。

どうです、このデザイン(*^_^*)。
最初はちょっと派手かな~~~、うるさいかな~~~、と抵抗があったけど、今はかなり気に入ってます。
6月 ×日(晴)
『求人情報サイトQ-JiN』の2011年5月度求人情報検索ワードランキングで、”動物病院”が一位だったみたい。
もともと獣医師は、一般の人に知られている以上に職域が広く、その一方で獣医師を養成する大学の数は戦後65年を経てもまったく同じですから、足りなくなるのも当然です。一部に人気職業ととらえる向きもありますが、それよりも慢性的に供給量が足りない、ということでしょう。
具体的な数値を挙げれば、獣医師の新卒は毎年わずか1000人たらず、この数は医師の10分の1、歯科医の20分の1程度ですから。
ちなみに今回の調査は、5月1日~5月31日までにQ-JiNサイト内で119,558回のフリーワード検索の検索ワードが対象だそうです。
ところで、数年前から獣医学部のない四国に獣医学部を設立する(=愛媛大学内)という案が文科省を中心になされていましたが、たとえこれが実現されても供給は満たされないことは明らか。
もっとも今の民主党が政権にいる限り、学部の増設は実現不可能だと思っています。
5月 ×日(晴)
世の中に愛犬家を名乗る人は多いけど、実のところオサマビンラディンもかなりの愛犬家だったみたい。
報道によれば、敷地内の農場には自活目的の家畜に混じって、多くのワンコもいたようです。
農場といっても基本的に自宅の庭ですから、牧羊犬というよりは愛玩目的だったのでは、と勝手に想像しています。
ところでビンラディンが実際にどんなワンコを飼っていたのかはわかりませんが、イスラム世界で今も昔も人気の犬種といえば、なんといっても「サルーキー」でしょう。

時速77km/hで疾走可能という精悍でスタイリッシュな風貌もさることながら、そもそも「サルーキー」とはアラビア語の古語で、「アッラーの神より与えられし高貴なるもの」、という意味だとか。個人的にも、サルーキーは大好きな犬種です。
5月 ×日(晴)
マスコミ報道によれば、先頃米国主導で行われた「オサマビンラディン殺害作戦」には、特殊部隊の隊員とともに、複数のエリート軍用犬が参加していたらしい。
秘密保持の立場から犬種や頭数などは一切発表されていませんが、任務の一部は爆発物の探知であったといわれていますが、これなら空港の検疫犬でもできること。エリート軍用犬を名乗るからには、何かほかに軍事的な特色があるんでしょう。

ところで史上初めて「軍用犬」を本格的に取り入れたのは、世界大戦時のドイツ軍です。米国もこの流れをくんでいるのでしょうか。
当時の軍用犬といえば、ジャーマン・シェパード。
ただ、その任務は悲惨そのもの。爆弾を背負わされたシェパードが敵の戦車の下にもぐりこみ、その接触で起爆装置が作動するというまさに自爆攻撃。
この話は子供向けの本にもなっていて、私も子供の頃、涙を流して読んだ記憶があります。
今回秘密のベールに包まれている米軍の軍用犬ですが、米軍の公表するところでは、被害は一切なかったとのこと。
米軍の殺害作戦はどうかと思うけど、唯一軍用犬に害が及ばかった点はよかったと思う。
5月 ×日(晴)
最近ユッケやだんごによる食中毒が騒がれています。
おそらくほとんどの人は知らないと思いますが、じつは獣医師は食品衛生や食中毒の専門家でもあります。

食肉処理場で解体された家畜の病気を発見したり、また病気ならばどこまで切除すべきか(=どこまで削れば食べられるのか)、あるいは内臓も含めて全て廃棄すべき状況なのか、包括的な判断はすべて検査責任者である獣医師の判断に任せられています。
現状を把握しているだけに、大学時代は病理や公衆衛生の先生方には「獣医師たるもの、レバー刺しなんて絶対食べてはいけません!」、としつこく言われました。レバーが刺身で食べられるほどの衛生環境で処理されてはいないことを先生方は熟知していたんですね。
レバーほどでなくとも、ユッケも衛生的な扱いがなされていなかったということでしょう。
ところで今回の事件とは直接関係ありませんが、レアで心おききなく牛肉が食べられるのは、おそらく日本を含む限られた国のみ。海外の牛肉には日本には存在しない特別な条虫2種が寄生していることが多く、レアでは危険です。
おいしいステーキ、国内ではレアでも海外ではウェルダンで頂きましょう。
5月 ×日(曇)
最近はワンコやニャンコに限らず、うさぎもかなり長寿になってきました。数年前までは、7歳以上といえば「長生きですね!」と言う会話が成り立っていましたが、今日では10歳以上が珍しくありません。
うさぎには定期的なワクチン接種こそありませんが、以前にも増して大切に飼われるうえに、今は不安があれば早い段階で病院を受診することが習慣化したこと、これこそが長寿の一番の理由だと思います。
ちなみに、うさぎの生物学的な寿命はおそらく5~6歳です。

ところで長寿化すると増える病気といえば、ガン。
ヒトに限らず、どんな動物でも高齢化するとガンが増えるんです。
最近はウサギの腫瘍切除手術もかなり多くなりました。ただ、ウサギの手術は手術以前の鎮静化や麻酔導入がとても難しいんです。
なぜならウサギは生物学的に非常にストレスに弱くできており、容易に心停止をきたす動物なんです。不用意に保定したり、つよく抱っこしただけで死ぬ可能性があります。
元々の意義は、もしも野生の状態で肉食動物等に捕食されたら、急激な心停止により必要以上に苦しまなくてもすむため、と言われています。
この1点をみてもウサギの本格的な診療の難しさが想像できると思いますが、それにしても、自然の知恵ってすごいと思う。
3月 ×日(曇)
福島の原発事故に終息の気配がなく、むしろ飲水制限から混乱は広がるばかりです。
都内の動物病院では、「水道水を愛犬に飲ませても大丈夫?」という電話相談が殺到しているとか。
長野県内では放射性物質による水の汚染はありませんが、当院でも軽井沢の別荘と都内を往復している方々からは、同様の質問を受けることが増えました。
この疑問に対しては、私も正直言って大丈夫か否か、本当のところはわかりません。少なくとも今の段階で、放射性物質(とくにヨウ素131、ヨウ素134)摂取による内部被爆と愛玩動物との関連性についての調査報告はありませんから。
むしろ私のほうが聞きたいくらいです。
ただ、ヒトについては疫学調査などをふまえて政府は「現段階で水道水は安全」とか「ヨウ素131を含む牛乳を1年間摂取し続けてもCT1回分の被爆線量で安全」と言っています。
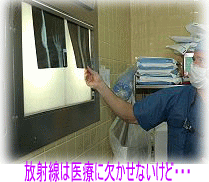
でも、これっておかしな論理です。
CTなどによる医療被曝は健康へのメリットが被爆による不利益を上回るから規制から例外的に除外されるのであって、必ずしも医療被曝=安全というわけではありません。
生体に対しては、被爆はないほうが好ましいにきまっています。
また、CTは基本的に外部被爆ですが、現在問題となっているヨウ素131、ヨウ素134は、いくら半減期が短いとはいえ内部被爆です。
この点については、チェルノブイリの医療支援の経験を踏まえて、阪大教授の野村氏が新聞紙上で政府対応に疑問を呈しています。
最近は動物でもCTによる画像診断が二次医療機関では当たり前になってきましたが、通常のX線検査より格段に被爆線量が多くなるので、取り扱いに際しては、よりいっそうの慎重さが求められます。
ここで国際放射線防護委員会(ICRP)によるCT取り扱いに関する注意喚起を記載します。
「胸部CTの実効線量は8mSvでこれは胸部X線撮影の400回分に相当する。そして骨盤部等のCT検査では20mSvにもなる。CT検査における組織吸収線量は、疫学調査でがんの発生率が増加するとされたレベルに近いかそれ以上になることもありうる。」
原子力発電所のトラブルが一刻も早く終息することを切に願う。
