8月 ×日(晴 )
今日は秋田犬の良太君(♂・1才半)が頸部を腫らせてやってきた。聞けば、散歩の途中でヘビに咬まれたとのこと。
その腫れがあまりに酷く、さすがに私もちょっとビックリ!
時間の経過とともに腫れが頸から顔まで及び、人相(犬相?)まで変わるくらいのひどい状態。しかもキズ口からの出血が受傷後6時間たっているのにもかかわらず、止まる気配がありません。まいったなこりゃ、即入院です。
いままでヘビに咬まれたわんこも多々診てきたけど、今回の良太君は今まででも一番過酷な状態かも。飼い主さんがパニックに陥るのも無理はありません。

おそらく今回はマムシによるものでしょう。佐久地方に生息する毒ヘビとしては、マムシとヤマカガシが有名ですが、ヤマカガシの毒は基本的に溶血毒ですから、せいぜい腫れてもソフトボール大です。
さいわい良太君は大型犬ですし体力もありますから、マムシに咬まれても適切に治療して処置を誤らなければ死ぬことはありませんが、小児頭大まで腫れた頚部が気管を圧迫して呼吸に悪影響を及ぼすようなら、今後一時的な気管切開も必要かもしれません。
マムシ、おそるべし!
7月 ×日(晴 )
小鳥の診療・・・その②
ここ5~6年で小鳥の診療は劇的に進化しました。
私の学生時代はもちろん、都内で代診していた頃は院長から、「小型鳥類(特に体重40g以下の鳥)には絶対筋肉注射をしてはならない」と厳命されていたものです。なぜなら、「注射の痛みで容易にショック死するから。」
これ当時の医学的常識。

ところがそんな中でも、古くから都内で小鳥の専門病院を開いていたT先生は積極的な治療で知られ、カナリアやセキセインコ、文鳥に対し筋肉注射どころか、なんと麻酔まで自由に使いこなしていました。
小鳥の診療では大変有名な先生で、十数年前の話ですが、あるTVドラマの中で、亡くなった小鳥がキリストのごとく復活して、大空に飛び去るシーンの撮影にT先生の麻酔技術が使われて、小鳥を熱心に診療する獣医師の間では、おそらくケタミン(注射用麻酔薬/麻薬)を希釈して注射したのではないか、と話題になりました。
私は晩年のT先生しか知りませんが、何回か東獣の主宰する講習会に参加した際、「鳥は皆さんが思っている以上に丈夫な生き物です。積極的に治療してください。」と口癖のように言っていたことを思い出します。
そのT先生も、もう亡くなられて久しい。
先生の遺志が後進に伝わったのか、あるいは時代の要請なのかわかりませんが、いまや小鳥の診療は「筋肉注射当たり前、必要に応じて点滴まで行なわれる時代」になりました。
現代は、小鳥にとってはかつて無いほど幸せな時代だと思う。
7月 ×日(晴 )
小鳥の診療・・・その①
今日はセキセインコのスピーチちゃん(♂・1才半)がやってきた。最近ろう膜(くちばしの根元のお肉の盛り上がったところ)の色が変わってきて心配とのこと。
セキセインコの場合、ろう膜の色で性別を判定しますが、スピーチちゃんは♂なので、もともとキレイな青色でした。
ところがここ1カ月で青が薄くなり、かなり肌色に近い状態。
困りましたね、これは。
セキセインコの場合に限っては、オスのろう膜の変化は明らかに内分泌疾患の兆候。その原因のほとんどは精巣の腫瘍化。
腫大化した精巣はレントゲンで確認できますが、痩せている子の場合、強い光源でお腹を透かすことでも確認できます。
スピーチちゃんの場合、かなり腹部も大きくなっており、およそ触診でも診断がつくレベル。
ここまでいくと、治療はかなり難しい。(>_<) 根治を望むなら手術ですが、小型の鳥類は麻酔が非常に困難。結局内科的な治療で対応せざるを得ないのが現実。 それにしても最近このような症例を多く診ます。個人的な感想ですが、なんらかの環境因子(化学物質?)を考えざるを得ない。とっても不安です。
7月 ×日(晴 )
この時期涼しいはずの軽井沢ですが、連日30度越えです。
暑苦しいのと早朝からのヘリの大音響で目が覚めた。
何事かと思ってTVをつけて確認したら、うちからわりと近い場所にある鳩山別荘に、韓国からキム・ヒョンヒ元死刑囚を迎えているらしい。そうか、この騒音は警備のヘリなんだ。それにしても朝から騒々しいな~。
こんな時は仕事に限ります。なぜなら1Fの病院エリアは動物の入院施設や併設ホテルがありますから、防音・断熱構造に加え徹底的な温度・湿度管理がなされており、実に静かで気持ちのいい環境。仕事もはかどるのだ。
一方2Fの自宅エリアといえば、さすがに病院エリアほどの重厚な防音・断熱構造はありませんし、差し込む日差しが大変強く、空調設備が24時間稼動していても、病院ほど快適ではありません。
というわけで、夜までうるさかったら今夜は病院のワンコ用ホテルで寝ようかな。
7月 ×日(曇 )
軽井沢も日中30度を越える暑い日が続いています。
こうなると途端に増えるのがワンコの外耳炎です。
以前はワンコの外耳炎といえば、アメリカンコッカーなどに代表される「好発犬種」がある程度限られていましたが、なぜか最近は犬種による偏りは少なく、むしろあらゆる犬種に満遍なく発生している感じ。
犬種にかかわらず、私たちの想像以上のレベルでワンコの体内では免疫力の低下が生じているのかもしれません。だとしたら状況は深刻です。
一方、以前は臨床症状から、外耳炎の原因となる細菌や真菌(酵母様菌)を推定できることも多く、治療に際し抗菌剤の選択で迷うことは少なかったのですが、最近は多くの抗菌剤に抵抗を示す細菌がとても増えてきました(多剤耐性菌)。
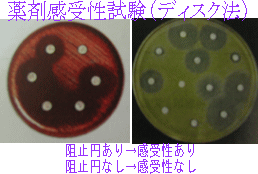
実際、薬剤感受性試験で「有効な抗生剤」を探そうにも、「あらゆる抗菌剤に完全な抵抗性をもつ細菌(=有効な抗生剤が無い!)」も珍しくありません。
このような耐性菌の存在は以前から知られていましたし、特定の抗生剤とこれに対する耐性菌の出現はいわば「永遠のイタチゴッコ」といえなくもないのですが、この急速な広がりを考えると、こちらも深刻!
外耳炎といえどもより慎重に治療する必要がありそうです。
6月 ×日(雨 )
今日はうさぎのミミちゃん(4才・♀)がやってきた。
以前当院で子宮蓄膿症の手術を受けた子ですが、これをきっかけにかなりの肥満体になってしまい、現在ダイエット中!
動物病院でダイエットをすすめるといえば犬や猫が圧倒的に多いのですが、最近はうさぎの肥満も非常に深刻です。
本来うさぎは野生では木の根のようなローカロリー・高繊維食を基本に生きていますが、いまのペット化されたうさぎの食事は明らかにハイカロリー・低繊維食にシフトしていますから、太るのも当然の成り行きです。
当然太っていいことはなく、さまざまな疾患を生じます。
ただ、うさぎは皮下脂肪が付きにくい一方、内臓に脂肪を溜め込む傾向が強いので、飼い主さんの中には「肥満です」と指摘されてもいまいち実感が湧かないようです。
とはいえ、日常的にうさぎを診療している獣医師に指摘されたら明らかに肥満なので、いままでの食事を見直す必要はあります。
さいわいな事に、うさぎは勝手に冷蔵庫を開けて自分で食べ過ぎることはないわけで、飼い主さんがうさぎの食事をちょっと見直すだけで効果的にダイエットが可能です。
そのポイントは以下の3点のみ。
1.食事の内容をアルファルファからチモシーに替える。
チモシー(イネ科の牧草)のほうが、よりローカロリー・低脂肪でうさぎの食性にあっています。ペレットもチモシーを主原料にしたものに替えればさらに効果的!
2.ペレットは量を決めて与える。ペレットでお腹が満たされるとチモシーや野菜を食べなくなり、異常発酵~消化器疾患を誘発します。
3.与える野菜はあくまで緑黄色野菜(水菜、チンゲン菜、小松菜など)にこだわり、人参やイモの類は最小限にしましょう。
炭水化物を含む食事は肥満の元です。

というわけで、ミミちゃん、ダイエットがんばってね。(^O^)
6月 ×日(雨 )
大学の会報誌が送られてきた。普段は忙しくてほとんどナナメ読みですが(というか、ほとんど読んでない・・・)、今回は今年現役を引退された”気になる先生お二方”のコメントが寄せられていたので、ここだけじっくり読みました。
まずは外科の教授、W先生。
私の学生時代第一外科の助教授で現役バリバリ、厳しいことで有名な先生でした。
外科の実習で最初に教わるのが手指の正しい洗い方。といっても、単純な手洗いではなく、外科の手洗いは歴史的に超有名な外科医の名前がついた難しい洗い方があって、動作が非常に厳密。
あえて例えるなら茶道のような完全に確立された様式美の世界!

実習後W先生の前で、ひとりずつ実演(=試験)するわけです。
わずかでも間違えると、「Nothing!」といわれて再度復習してまた列の最後尾に並ぶ。「OK!」をもらった者から実習終了(=すなわち帰宅)が許可されます。
私はなんとか早めにクリアできたクチですが、不器用な学生は昼の1時に始まった実習が、夜8時半ころまでかかり(なんと手洗いに7時間半)、W先生にコッテリ絞られるという伝統のデスマッチ。ああ、懐かしいなあ・・・。
もうお一方の先生は大学病院副院長のO教授。私の在学中は第三内科の助教授でした。W先生とは対照的に(?)じつにおだやかな講義をする先生でした。内科の試験答案もつねに好意的に解釈してくれて、学生の間では「オニのW先生、仏のO先生」と評されていました。
6月 ×日(晴 )
前回鎮静剤だけで歯科処置を行なうことも多いと書いたところ、これに関する複数の問い合わせをいただいたので、この場で新たに補足説明致します。
動物(主に犬や猫やウサギやハムスター)を対象に、じっくりと口腔内を観察したり、残存する乳歯を抜歯したり、歯石を除いたりする場合、患者である動物の安全性を確保しつつ、術者の作業を迅速かつ確実に行なう為には、「患者の不動化」は必須です。
その際、不動化を得るためにどのような処置を選択するのかは獣医師個人の経験に大きく左右されますが、大きく分けて2つの方法に集約されます。
1) 全身麻酔による完全な無意識下でおこなう。
2) 鎮静催眠剤や鎮痛剤の併用等により、意識を消失することなく、患者の動きを最小限に抑えて行なう。
この2番目の方法が一般にセデーションと呼ばれるもので、全身麻酔に比べると循環器や呼吸器に対する負担が少なく、全身麻酔のような、厳密かつ完全な麻酔管理を必要としません。なによりある程度の意識が保たれ高齢動物にも安全に使える、麻酔事故のリスクが限りなくゼロに近い、といったところが最大の特徴です。
したがって一般論として、入院を必要としない日帰りで行なわれるキズの縫合や、組織の生検、前述のスケーリング等に適しています。
一方、口腔内に発生した悪性黒色腫の切除、ガマ腫の切開、下顎骨折の整復手術など、より侵襲性の高い手術や長時間を要する複雑な手術では、セデーションのみでは事実上作業が不可能であり、全身麻酔が必要です。
かなりおおざっぱな言い方になってしまいましたが、いずれの方法も一長一短あり、臨床の現場では個々の状況に応じて使い分けています。
当院では、歯石の除去やウサギの過長歯のトリミングなどは基本的に入院は必要としない(=日帰り可能)処置とみなし、その際には特別な事情のない限り、鎮静剤の投与のみ、もしくはこれに鎮痛剤を併用することで、高い安全性を確保しています。
6月 ×日(晴 )
医療機器の寿命って・・・①
とうとう超音波スケーラー(=歯石を効果的に取り除く機械)が壊れてしまいました。(>_<)
開業以来まる6年間、酷使し続けたのでこわれても仕方ないと納得する一方で、愛着のある使い慣れた機器を手放すのは、たとえるなら愛車を手放す時と似て、とっても残念・・・。
もっとも、当院では、あえて全身麻酔を使わず、セデーション(鎮静催眠剤投与のみ、もしくはこれに鎮痛剤の併用)でスケーリング(=歯のお掃除)をすることが多いうえに、歯科診療にも力を注いでいるので、この機器の使用頻度が一般の動物病院に比べてかなり高いことも事実。明らかに寿命がきた~~~、といえます。
こうなった以上、早急に代替機を購入せねば!
業者に依頼したら、即日デモ機として最高の機材を用意してくれました。高級機種だけあって、従来のスケーリング機能に加えて、ゴルツエチップという無血抜歯用チップも備わって、全体的にかなり使えそう 。\(~o~)/

超音波スケーラーとしては結構いい値段だけど、うん、気に入った!(^_^)v
いい仕事をするためには、いい道具が欠かせません。よし、これを購入しよう!ビックカメラで大型TVを購入するときと同様、相変わらず即断即決のワタシでした。
6月 ×日(曇 )
獣医学部は人種のるつぼ? ②
獣医学部の学生はユニークな家庭の出身者が多く、前出の政治家などは序の口で、皇族に連なる方や有名実業家一族出身も珍しくありません。
その中でも極めつけはなんといっても霊媒師でしょう。その方の親御さんが名の知られた霊媒師でした。
さすがにそのスジの超有名人だけにここで名前までは挙げられませんが(とんねるずの石橋がよくモノマネしていました)、かつて獣医師国家試験のヤマをこの方にお願いして当てていただこうか、などと友人たちと話し合ったことを昨日のことように思い出しました。
