6月 ×日(曇 )
獣医学部は人種のるつぼ? ①
午前中の仕事を終えて、遅めの昼食を取っていたら、菅直人氏が総理に選出されたと伝えていました。
菅氏といえば、私たち獣医師の間では、ご子息が獣医師であることは広く知られています(臨床にたずさわっているかどうかは知りませんが)。
おそらく口蹄疫が発生した際には、畜産・食肉業界にどれほどの打撃を与えるか、ご子息を通してその危険性を当初から十分把握していたのではないでしょうか。
週明けには組閣にのぞまれるようですが、もう赤松大臣のような家畜伝染病に関して危機意識を欠いた人物だけは農水大臣には任命して欲しくない、と多くの獣医師は感じているはず。
ところで獣医学部はなぜか以前から政治家の子息が多く在籍し、私がいた頃も父兄会名簿をパラパラめくると父兄の職業欄に「大臣」とか、「市長」といった記載が目立ちました。
さすがに職業欄に「総理大臣」との表記を見つけたときは悪い冗談かと思いましたが、とんでもない、父兄欄に記載された名前は当時金丸氏に担がれた総理大臣・海●俊○氏でした。
ところで私が卒業する頃にはもう、父兄会名簿は発行されなくなりました。個人情報保護の観点から廃止に至ったとのこと。ある意味とっても残念なのだ!
6月 ×日(晴 )
今日はアメリカンコッカーのビーナスちゃん(♀・10才)がやってきた。飼い主さんいわく、「最近咳がひどく、夜もちょっと息苦しそう」とのこと。
念のため心エコーで検査したところ、典型的な拡張型心筋症(DCM)であることが判明!これでは夜どころか昼間も息苦しいでしょう。

この拡張型心筋症は従来ボクサーとドーベルマン・ビンシャーに特異的と言われてきましたが、じつはアメリカン・コッカーにも多発する病気で、現在原因は不明とされていますが、個人的には遺伝的な疾患と疑っています。
ただ、アメリカン・コッカーのDCMに限って、タウリンやカルニチンを強化した食事で卓効を示すことも多く、この点で、ボクサーやドーベルマンピンシャーのDCMとは発病の仕組みが異なるとも言われています。
もっとも、DCMは犬種に偏りがあるもののどの犬でも発症の可能性はありますから、高齢犬で頑固な咳が止まらない、一般的な心不全の治療で体調が改善しない、など重い症状が認められた場合には、心エコーなどで徹底的に心臓を診てもらうことをおすすめします。
5月 ×日(晴 )
食道の病気 その②
以前はほとんど注目されることが無かった食道の病気。最近は内視鏡などの発達で診断率が上がっていますが、バイオプシーが難しい、エコー診断が使えない、多くの場合X線頼み、等の理由から依然として扱いにくい疾患です。
基本的にワンコに多い食道の病気といえば、巨大食道症と逆流性食道炎。逆流性食道炎はワンコに限らず、ここ5年くらいでヒトの臨床でも激増している注目の疾患。
たしか、日経メディカルのリサーチによれば、全国の内科医に対するアンケート「過去3年以内でもっとも多く診断した消化器疾患はなんですか?」に対し、逆流性食道炎は過敏性腸疾患と並んでぶっちぎりの1位・2位を記録していたと思う。
もっとも、ワンコの場合逆流性食道炎の原因はヒトのように生活習慣や肥満に起因することはなく、じつは医原性(=医療が原因をつくる)が多いみたい。
具体的には、手術後の嘔吐による胃液の逆流が指摘されています。一時期、避妊手術に際し、腹腔内の臓器を頭側に移動させて術野を広く確保する理由から、麻酔時に頭をかなり低く保つ体位を推奨していた某国立大学の教授がおりましたが、いまはどうしているのかな~?これって、いまでは危険因子として認識されています。
ただし、この方法はあまり普及していません。やっぱり自分が手術を受ける立場で考えても、他に方法がないのならばともかく、術者の都合だけで頭に血がのぼるような不自然な姿勢は好ましくない、・・・そう大多数の獣医師は感じていたのだと思う。やっぱり獣医師は動物に優しい人種なのだ。
5月 ×日(晴 )
食道の病気 その①
今日はMダックスのユキオちゃん(7才、♂)がやってきた。
りん告によれば、食欲もあって飲水も普通なのに嘔吐が酷く痩せる一方とのこと。吐き方が異常なので大変心配になり、今日まで近くの病院で胃腸炎を疑って検査・治療してきましたが、まったく改善せず、ほとんどさじを投げられたみたい
。
参ったな、こりゃ。もうかなり衰弱している様子から、原因だけでも突き止めなければ、どう考えてもやばいだろう。
改めて検査入院してもらって徹底的に調べてみたら、なんとユキオちゃんは食道疾患(=巨大食道症)であることが判明!前の病院では胃腸に注目するあまり、食道疾患に思い至らなかったのでしょう。思い込みってコワイですね。臨床にたずさわるかぎり、他人事じゃありません。
ところでこの疾患、なぜか最近ダックスに多いんです。
もっとも、米国ではMダックスの消化器疾患の25%は巨大食道症とも言われかなり一般的な疾患とか。
一方日本国内ではここまで多くはないと思われますが、最近は食道疾患に注目が集まっていますから、今後診断される数も増えることでしょう。
5月 ×日(曇 )
宮崎県の口蹄疫が、今日も猛威をふるっています。
マスコミではなぜかほとんど報道されていませんが、コトがコトだけに獣医師間ではさまざまな情報が飛び交い、私のところもメール等を通じて内情が伝わってきます。いまも奔走している産業動物担当獣医師は宮崎県内の酪農の全滅をも覚悟しているとか。そこまで事態は深刻です。
しかし、ここまで口蹄疫が大規模に流行するとは・・・。
大学時代、口蹄疫を含む家畜法定伝染病26疾患は国家試験で常に問われるため、病因・疫学から診断に至るまでしつこいくらい詳細に覚えさせられた記憶があります。(詳細を知りたい方は下記アドレス参照のこと)
http://www.niah.affrc.go.jp/disease/fact/03.html
ところで、大学では上記法定伝染病の治療について学ぶことはありません。なぜなら摘発・淘汰(=全頭殺処分)が鉄則であって、治療は必要ないのです。それだけこれらの病気がひとたび流行すると、産業界に甚大な被害が生じるということです。
この口蹄疫、じつは最初に確定診断が得られたのは、今年3月のことでした。
初期の段階でいきなり口蹄疫を疑って検体を採取した獣医師は、かなり優秀なドクターだと聴く。
ところがこれ以降今日に至るまで政府の対応は後手後手に回り、有効な手立てを講じることも無く、初期の封じ込めに失敗。
ところで、農水省の責任は極めて重大なのに、自ら陣頭指揮を執るべき赤松農水大臣はなぜか優雅に外遊とか。困ったものです。
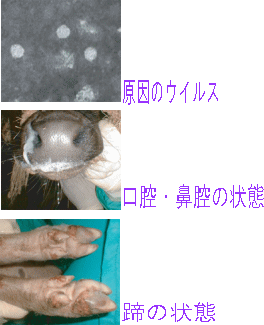
4月 ×日(曇 )
今日はウサギのモモちゃん(♀・4ケ月齢)がやってきた。
やんちゃなモモちゃんは、飼い主さんが洗濯物を干すために
二階のベランダに行く際には、必ず後に付いていくのが日課です。
今日も飼い主さんを追いかけて、
いつもどおり階段をかけ上がったところ
運悪く足を滑らせ転落し、左の後ろ足を痛めたらしい。
でも来院時すでに症状(疼痛)は緩和しており、
大事に至らなかったのは不幸中の幸いでした。
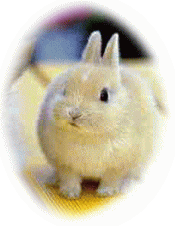
ところで意外に思われるかもしれませんが、
ウサギは種類によっては結構人になれてくれます。
特に幼い頃から可愛がっていると、
まるで鳥類の刷り込み現象のような懐き方をして、
家中どこに行くのにも付いて来るようになりますよ。
4月 ×日(曇 )
ヒルズの新薬発売一周年記念の学術講習会に行ってきました。場所は品川駅近くの東京コンファレンスセンター。
講演の前半はT大薬理学教室H准教授のお話。分子レベル、細胞レベルでのかなりマニアックな内容で、かつての薬理の授業を思い出しました。(-_-;)
必ずしも臨床向きの内容ではないけれど、しっかり理解していると知識が深まり、結果として病態を正確に把握できるといったところでしょうか。暗室でのスライド上映のため、うとうとしている人もチラホラ見かけました。前日、遅くまで仕事していたのかな~?
さて、講義の後半はT大内科のO准教授のお話。
やっぱり参加者は臨床家主体なので、俄然みんなの目が輝いていました。聴講者は500~600人前後はいたと思うけど、驚くほどみんな真剣に聞き入っていました。無理もありません、たしかに講演内容が充実していてなおかつ面白かった。
企業の主宰する講演はとにかく薬の宣伝になりがちだけど、O准教授のように、必ずしも薬の紹介にとらわれず、その日一番話したい話題を、それも最新の知識をまじえてみっちり話すというのは素晴らしいと思う。
やっぱりO先生の講演は面白い!
4月 ×日(雨)
内視鏡のお話 その② 米国編
私が以前からラパロ(腹腔鏡)に強い関心を寄せていることを知っている業者が、今日はいろいろ資料を送ってきた。さすが業者は気が早い。先端技術好き、機械好きな私の性格を完全に読みきっている。
ところでこの資料の中に1枚のDVDが含まれていました。内容としては、この春米国の動物病院で行なわれた手術風景(ラパロによる卵巣・子宮摘出術)が収録されていました。
さっそく動画で再生して見ました。
手術設備からみて、かなりの症例をこなす優良病院とみた。
手術そのものは実に手馴れている様子で、術中なんら問題はありませんが、一番驚いたのは、執刀医の先生、手術が佳境に差しかかると、いきなり口笛を吹く、という行為。実にノリノリ、怖いくらいノリノリなのである。
手術室内で生体モニターの電子音やシーリング確認時の電子音に混じって、執刀医の先生の口笛がヒューヒュー聞こえてくる!
しかも中途半端な口笛じゃなくて、フシまわしがつけられて完全にメロディー。
ときどき冗談を言い合って、スタッフ一同大爆笑しながら、あっという間に手術終了。その間わずか20分。
さすがアメちゃん、、なんとも陽気である。大学時代・代診時代をを含め、今まで飽きるほどいろんな手術を見て来たけど、こんなに楽しげな手術風景ははじめて見た。
これって国民性の違いなのか、はたまたスタッフの性格なのか、見終わっても別の意味で興味が尽きなかった。
追記:
後日米国人の生態(?)にあかるい人の解説によると、アメちゃんの仕事中の口笛は必ずしも珍しいものではなく、医師に限らず日本で働く外資系金融機関のエリートサラリーマンなども、仕事が好調な時は自然に口をついて出てしまうとのこと。要はノリノリなんですね~。
ちなみに手術室での冗談は、スタッフの過度の緊張を和らげて、チームに一体感を持たせるための執刀医の責務、という説があるようです。本当かね?
4月 ×日(雨)
内視鏡のお話 その① 国内編
最近外科系の学会に行くと必ず話題に上るのがラパロ。医学界・獣医学界ではいまやとってもなじみの深いコトバですが、ご存じない方に改めて説明しますと、これは腹腔鏡という内視鏡をお腹に刺して行なわれる、より侵襲の少ない手術のこと。
(Laparoscopic surgery)
以下の画像は、実際にお腹に設置される最新のポート(器具の挿入を行なう入り口の役目をはたす)です。

このラパロ、ヒトの世界ではかなり普及していますが、獣医学領域ではいわゆる先端技術ですから、日本国内ではまだほとんど普及していません。
一方、米国獣医界ではある程度普及しており、避妊手術のほか肝臓・胆嚢の手術に汎用されているようです。
もっとも、米国で認められた医療技術はわりと早く日本国内に導入される傾向がありますから、今後は国内でも広く普及するのかな?
4月 ×日(雨)
新たに獣医学部誕生?
愛媛新聞の報道によれば、近い将来四国にはじめての獣医学部が設立されるらしい。四国には獣医師養成機関が存在しなかっただけに、これはいいかもしれません。
近年獣医師不足が急速に進んで(特に公衆衛生や食肉行政に携わる公務員獣医師)、全国各地に悲鳴を上げる自治体が増す中、いよいよ国も本格的な獣医師増加を目指して動き出したようです。
農水省は今月2日までに、獣医療の体制を整備するためのむこう10年間の基本方針案を公表し、獣医師会に対し労働環境の重点整備を約束しましたが、目的はもちろん行政にたずさわる獣医師の確保。
もっとも、焦ったところで獣医学部は非常に少なくて全国で年間1000人くらいしか卒業しませんし、卒業生の6割はこの不況下でも臨床志向ですから、今後20年くらいは確実に深刻な地方公務員獣医師不足が続くといわれています。
このような状況下で、新たな獣医学部の設置は問題の解決につながるのでしょうか?
以下は愛媛新聞からの抜粋です。
愛媛県と今治市が構造改革特区制度で国に提案していた今治新都市への大学獣医学部設置許可について、過去4回の提案を「対応不可」と門前払いしてきた文部科学省が、5回目の提案に対する最終回答(2月23日付)で「提案の実現に向けて対応を検討」と従来とは異なる姿勢に転じたことが9日、分かった。
同日の県議会本会議で、本宮勇氏(自民、今治市・越智郡区)の一般質問に対し、高浜壮一郎副知事が明らかにした。(愛媛新聞)
